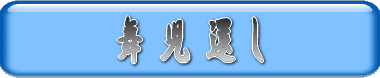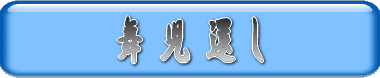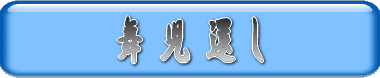
舞児還しは三嶋神社に於ける最大の神事として年々盛大に行われるようになっていった。ところが昭和48年、2人の死者を出す事故が発生してしまい、警察から祭典の中止を求められた。
舞児還しどころではない。祭りがやれるかやれないかの瀬戸際に立たされたのである。
翌昭和49年には祭典改革委員会が新たに設置されて約50回にも及ぶ改革会議を行い、祭典規約の全面改正、絶対無事故宣言、そして全社舞児還しの遂行が決議された。
これは決して祭りを盛大にするなどという目的ではなく、三嶋神社最大の神事である舞児遺しに対して真剣に取り組む事によって、“神事をまっとうする姿”を警察と世間に認めてもらうためのものであった。
舞児還しをやるからには当然“舞”を奉納しなければならない。今まで氏子6社に対して4人の乙女舞であったが、新たに谷本社、凱生社、慶雲社、睦栄社を三嶋神社の準氏子とし、6人の浦安舞(うらやすのまい)を増設した。浦安舞とは昭和15年「皇紀2600年」祝典の際に作られ、12才の女子、8人又は4人で行われる舞である。上代の戸振を偲ぶ荘重典雅な舞であり、扇の舞と鈴の舞があるが、三嶋神社では鈴の舞を採用している。
その後昭和55年に鳳雲社と龍生社の加入により、2人の浦安舞を増設した。そして昭和59年には湧水社が独立したが、浦安舞はすでに8名の定員に達していた為、朝日舞(あさひのまい)を1人増やし、更に昭和62年には藤雲社の独立により朝日舞をもう1人増やしている。
朝日舞は浦安舞同様、神社本庁で管理されて全国的に行われている舞であり、9才の女子が舞う乙女舞である。神社本庁とは東京渋谷にあり、昭和21年、国家神道廃止に伴い設立され、全国の神社の大半を組織している。
従って現在は氏子10社のうち4人の乙女舞、2人の朝日舞、そして4人の浦安舞が各社から順番で選出され、準氏子4社からは各社1名ずつ4人の浦安舞が選出されるというわけである。
前ページへ
戻る
次ページへ