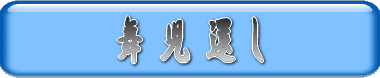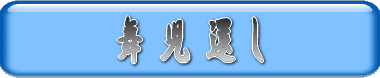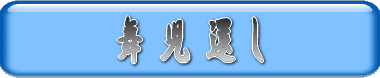
今や、遠州地方はもちろん、全国的にも注目を浴びている舞児還しであるが、そのやり方には各社様々な特徴がある。
例えば桑水社、藤雲社、湧水社は昔の桑水社の流れをくみ、社長の提灯の持ち方に自然と出来上った決まりがある。
舞児遺しで屋台の引き回しを行っている間、欄干に乗っている社長は、左手に持った提灯を斜め前に突き出し、肘をピンと張ってなくてはいけないというのだ。社長らしい堂々とした姿勢がいいというのだろう。
ところが、この位置で提灯を持ち続けるのはかなり困難である。提灯の重さに腕の筋肉が耐えられず、ぶるぶると震えて次第に肘は曲ってくる。すると「社長!肘が曲がってるぞ。もっと提灯を前へ出せ!」のヤジが飛ぶ。これもひとつの伝統だから仕方あるまい。
北街社には屋台の乗り方に特徴がある。欄干への乗り方であるが、舞児を屋台の中央に乗せ、左側に社長、右側には氏子総代、又は神社担当が乗る事になっている。
この場合、舞児が乙女と朝日の時は氏子総代が、浦安の時は神社担当がそれぞれ乗り、社長と氏子総代(神社担当)は立って提灯を持っているのが普通であるが、北街社だけは舞児を中央に乗せて両者は座わる。
「舞児のお披露目なのだから、社長が目立ってはいけない」と北街社はいうのだ。なるほど一理ある。鳳雲社はこの考え方に習い、乙女・朝日の時は座わり、浦安の時は立つというやり方をとっている。
また凱生社は、舞児還しの時に必ず“宮ばやし”をやることがその特徴となっているが、これも自然発生的に始まったものであり、いつ頃から行われて来たの
か定かでない。
その他、舞児のおろし方や、舞児帰宅式のやり方も社によって若干の違いはあるものの、“舞児還し”という三嶋神社の神事を”まっとう”していることに変
わりはない。
これからも「森町の伝統文化」として受け継がれて行くだろう。
前ページへ
戻る